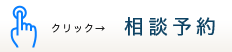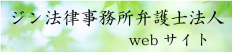FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.国際労働問題の準拠法は?
労働関係での準拠法が問題になった事例を紹介します。
外国法人との労働契約で、契約上の準拠法は海外によるとの記載があったケースです。
東京地裁平成28年9月26日判決の紹介です。
事案の概要
原告は、平成16年からある会社と雇用契約を締結し、金融ブローカーとして、英国で働いていました。
その会社は、平成17年に被告会社(英国法上のリミテッドパートナーシップ)に買収。
平成20年6月、原告と被告会社は、それまでの契約から、あらたに雇用契約を締結。
その契約では、英国法を準拠法とする条項、別途合意がなければ4年後に自動的に、雇用期間が1年間更新されるという条項、契約終了には各当事者が契約期間または更新期間の最終月の最後の2週間以内に通知する必要があり、通知後3か月が満了した時に雇用が終了する条項がありました。
原告は、その後、英国と日本を行き来する生活になり、被告会社(米国デラウェア州法人)の日本支店でも勤務。
原告には日本を本拠に。
被告会社は、平成23年1月に原告を被告会社日本支店に出向させる形に。
平成24年5月、被告会社は、原告に対し、雇用契約が同年6月で期間満了することを理由に、新たな契約条件を提示。
原告は未回答。
平成25年5月、被告会社らは、原告に対し、雇用契約が既に終了している、仮に終了していないとしても、再雇用しない決定をしたと通知。
原告が、契約の不更新について、英国法上でも日本法上(労基法14条)でも無期雇用に転化した、不更新は解雇権の濫用として無効だと主張、労働契約上の地位の確認、不当な賃金の減額を理由に、未払賃金等の請求を求めました。
裁判所の判断
一部認容、一部棄却という結論でした。
まず、労働関係についての準拠法が問題になります。
原告と被告会社の雇用契約の準拠法は、当事者の選択により英国法となります(法の適用に関する通則法〔以下 「通則法」〕7条)。
もっとも、原告が、日本の労働法規を適用すべき意思表示をしていることから、通則法12条1項により、労働契約の成立及び効力について、日本法のうちの特定の労働法規の適用ができるかが問題となります。
通則法12条1項は、労働者の意思表示により、特定の強行規定を適用するための要件として、最密接関係地法であることを要するとしているため、本件雇用契約における最密接関係地法が英国法と日本法のいずれであるかが問題となるのです。
通則法12条2項は、労務提供地の法を最密接関係地法と推定する旨定めているところ、その趣旨は、労働契約の継続性や集団性に鑑み、同一の職場で働く労働者と同等の保護を保障しようとするものと解されます。
このような趣旨からすれば、労務提供地は、現実の労務の提供がどこでされたかを基に判断すべきものと解されるとしました。
ところが、本件では、最初は英国、その後、日本で働くという経緯があります。
労働契約継続途中に労務提供地が変わった場合には、新たな労務提供地の法を最密接関係地法と推定することが可能であると解されるところ、本件では、平成21年7月以降約3年2か月の間継続的に専ら日本で勤務していたことから、労務提供地が変わった場合に当たり、日本を労務提供地と認めることができるとしました。
雇用契約の終了の適法性は?
解雇権の濫用禁止(労働契約法16条)や有期雇用契約の雇止めに関する規制(労働契約法19条)等の雇用契約の終了に関する規制は、雇用期間の定めに関する規制や、これに基づく労働者の地位と一体となって定められているものということができると。
そうであるにもかかわらず、1個の雇用契約についての雇用の終了という一つの場面に関して適用される法を分断し、雇用期間の定めに関する規律のみ英国法に準拠し、雇用契約の終了に関する規律は日本法に準拠するという判断の枠組をとることは、法律関係をいたずらに複雑にする上、当事者の予測が及ばない不合理な規律を形成して、その適用を可能とするものであって相当性を欠き、にわかに採用し難いとしています。
本件雇用は有期雇用と認定し、有期労働契約の更新拒絶に関する実定法及び判例法理を適用して判断するとしました。
そのうえで、被告会社による不更新の通知による雇用契約の終了について労働契約法19条各号に該当する事情はなく、不更新の通知をした後3か月が満了した時に本件雇用契約は終了したものというべきであると認定しました。
準拠法について原告の主張を認めたものの、雇用契約上の地位については否定という結論でした。
通則法による準拠法
本判決では、英国法を準拠法としていた雇用契約について、通則法12条1項・2項により、労務提供地法の日本法上の労働契約法を適用しました。
同様の判断をしていた裁判例もありますが、本件では、労務提供地が途中で英国から日本に変更されていたという事情がありました。
本判決では、新たな労務提供地である日本法を最密接関係地法と推定することができるとした点が特徴です。
労働契約でも、当事者は合意によって準拠法を選択できます。
しかし、労働契約の場合、労働者と使用者との間には、力の差があり、公平な契約ができない可能性を前提として、労
働契約に最も密接な関係がある地の特定の強行規定を適用すべきだと労働者が意思表示した場合には、そちらが適用されるのです。これが通則法12条1項の規定です。
労働契約については、労務提供地法を最密接関係地法と推定しています(通則法12条2項)。
横浜駅近辺で労働問題の法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。