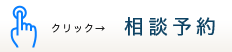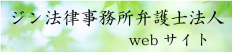FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.民事裁判で確定判決の既判力とは?
民事裁判の確定判決には、既判力というものがあります。
判決を蒸し返すことができないので、裁判では、しっかり主張・立証しておく必要があるのです。
この既判力について解説していきます。
民事裁判全般の解説はこちら。
既判力とは判決を蒸し返せない力
既判力とは判決の効力の一つです。
民事裁判での判決がでると、それには一定の効力が生じます。
その中で、既判力は、判決の蒸し返しができないような効力のことをいいます。
わかりやすく言えば、蒸し返しの禁止作用です。これが既判力の意味です。
この既判力の作用により、裁判の当事者は、確定判決の判断に反する主張をできなくなるのです。
判決が確定することで、基準時までにあった事由に基づく主張や抗弁を、あとから別の裁判で提出することはできなくなるのです。
つまり、基準時より前の事由をもち出せないことになります。
そのような事由は、最初の裁判で出しておきなさいというルールです。
既判力が認められる理由
判決が確定しても、後から別の裁判を起こして、その判決の内容を無視して判決を言い渡されるとすれと、いつまでたっても、当事者間の紛争は解決されません。
裁判の意味がなくなってしまいます。
当事者の権利利益の保護や、紛争の解決という観点から、このような既判力が認められているのです。
既判力の民事訴訟法での条文は114条
確定判決の既判力は、民事訴訟法に書かれています。
条文は114条。
1項には、「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する」とあります。
確定判決が既判力を持つものであること、主文に包含するものという客観的範囲を決めています。
既判力は確定判決が持つもの
まず、既判力は、「確定判決」が持つとされています。
判決は、言い渡されても、すぐに確定しません。
判決に不服のある当事者は、控訴など上訴できます。不服申立てをして、その判決の取消しや変更を求めることができるのです。
このような上訴が尽きた場合に、判決は確定します。
上訴期間の2週間が過ぎたり、3審制で最後の裁判所での判決などで、上訴の方法は尽きたことになります。
裁判の途中で出されるような、中間判決には既判力はありません。最終判断の終局判決に限られます。
また、判決ではない決定類、たとえば、訴訟指揮に関するものや競売開始決定などには既判力はありません。
仮処分などの民事保全事件における裁判も同じく既判力はありません。被保全権利について判断がされても、既判力はなく、本案の裁判所を拘束しません。
支払督促に既判力はない
確定判決と同一の効力を有すると条文にかかれている制度もあります。
これらは、既判力を持つのでしょうか。
確定した破産債権の債権表の記載(破産法124条3項)などは、既判力を持つとされます。
和解調書、請求の放棄または認諾調書については、確定判決と同一の効力を有するとされていますが、既判力については見解が分かれています。
これに対して、確定判決と同一の効力が認められるものの、裁判所書記官の処分の場合、既判力は認められません。
仮執行宣言付支払督促や訴訟費用額確定処分などです。これらには既判力はありません。
既判力違反の訴えは却下
同一当事者間における同一請求についての訴えは、前に出された確定判決の既判力によって、請求が棄却されたり、訴えが却下されます。理由なく勝訴した裁判を繰り返す場合には、訴えが却下となります。
同日事件で、争うことができないという既判力の作用は、後日の訴えを起こされた際に、被告が既判力による主張をし、裁判所がこの主張を認め、請求を棄却するという結論になります。
後訴で同一事項が争いになった場合、当事者はこれに反する主張をすることができません。この効果のことを、既判力の遮断効とよびます。
確定判決の既判力に気づかず判決が下されてしまった場合はどうなるでしょうか。
その判決の判断が過去の判決の既判力に抵触している場合、後訴の判決は確定しても、再審の訴えで取消しを求めることができる(338条1項10号)とされています。
既判力の客観的範囲は主文
既判力の拘束力が生じるのは、判決主文にかかれている判断事項だけです。
民事訴訟法では、訴訟物と呼ばれるものです。
条文では、「主文に包含するもの」とされています。その意味は、判決主文に表現された判断の範囲というもので、原告の請求についての結論的な判断、つまり、訴訟物とされているのです。
既判力は判決の主文で表現されている判断事項にだけ生じるので、判決の理由中の判断は、原則として対象外。既判力は及ばないことになります。
既判力は判決主文だけ見てもわからない
既判力は客観的範囲となる主文ですが、実際の判決主文を見ても、それだけではわかりません。
原告敗訴の場合、主文は「原告の請求を棄却する」というものです。
お金を払えという原告の請求を認める判決の主文も「被告は原告に金●円を支払え」というものです。
主文の文言だけみても貸金なのか損害賠償なのかもわかりません。
既判力の内容を確認するには、裁判所の結論的判断が何か、判決の事実や理由の欄の確認しなければならないのです。
判決理由中で裁判所のした判断に既判力は生じませんが、客観的範囲を確認するには、理由まで確認する必要があるのです。
既判力は判決理由には生じない
主文に表示された判断以外、判決理由でされただけの判断については、既判力は生じません。
判決の理由中では、前提となる事実などで確定された事実が書かれています。
こちらも、請求そのものではありません。主文に包含されるものではないので、既判力は生じません。
主張の前提となる法律関係について、理由中に記載されていても、既判力はありません。
たとえば、利息の請求をした訴えのなかで、その元本債権の有無について理由中で判断されたとしても、既判力の観点からすれば、後から別訴訟で元本債権の有無を争うことはできるのです。
既判力と一部請求
裁判では、一部請求という訴えがあります。
5000万円の権利を持っているものの、1000万円だけ請求するという裁判です。
このような場合、判決の主文で判断されるのは、1000万円の請求権です。では、既判力はどうなるのでしょうか。
裁判所の考え方は、一部請求と明示された請求が認容された場合には、残部請求については既判力が生じないというものです。
一部請求で外された4000万円の請求部分については、既判力が及ばないので、別訴提起ができるというものです。
逆に、認容されずに、一部請求が棄却された場合は、既判力ではなく、信義則を持ち出して、制限するのが裁判所の立場です。
訴えの取下げと既判力
訴えが取り下げられた場合、確定判決とはならないので、既判力は生じません。
訴えは、一審などで終局判決が下された後でも、確定するまでは取り下げることができます。
しかし、このように、終局判決が下された後に訴えを取り下げるときは、再び同一の訴えを提起することは許されない規定があります(民事訴訟法第262条第2項)。
既判力の問題ではなくても、判決後では、同一の訴えは制限されることになります。
既判力の基準時は事実審の最終口頭弁論時
既判力は、一定基準時までに主張できた事実に基づいて、裁判を蒸し返すことはできないという作用です。
逆に言えば、基準時以降の事柄であれば、裁判所はいまだ判断していません。基準時以降の事柄に基づいて、新た裁判をすることはできます。
民事裁判は、ある時点における権利関係を明らかにするものです。
この基準時はいつでしょうか。
これは、事実審の口頭弁論の終結時とされています。
地方裁判所が1審の事件であれば、高等裁判所が事実審となります。最高裁は法律審なので、高等裁判所の口頭弁論終結時が基準時になります。
いつまでに発生した事情に既判力が及ぶのかというと、この基準時までなのです。
この効果を既判力の遮断効と呼ぶこともあります。
たとえば、貸金裁判で、口頭弁論終結前に返していた事実があるなら、それを主張しておかないといけません。後日、別の裁判で争おうとすると既判力でダメになります。これに対し、裁判後に返した事実は、別の裁判でも主張できます。過去の裁判では、まだ返していなかったので主張できなかった事実となり、既判力は及ばないことになります。
既判力は誰に及ぶのかという人的限界
既判力は、裁判の当事者となって争ったことによって本来発生するものです。
全く関係のなかった第三者に及ぶものではありません。自分の知らないところで争われた裁判の効果が及ぶとしたら大変です。
既判力が誰に及ぶのかという問題は、人的限界という言葉で語られることが多いです。
これは、民事訴訟法115条に書かれています。
既判力が及ぶ対象者として、
1 当事者
2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
3 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
4 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
とされています。
原則として、当事者である原告・被告の間にだけしか及ばないものです。
不正な判決には既判力は生じない
判決を不正に取得する不法行為があります。
被告の住所が不明だと偽って裁判を起こし、公示送達によって送達させ、被告に反論の機会を与えずに判決を取得する方法です。
また、第三者と通謀し、第三者の住所を被告の住所だと偽って提訴し、裁判書類を受領させ、被告に反論の機会を与えずに判決を取得する方法です。
このような不正な判決には、既判力等裁判の効力を否定した裁判例があります。
既判力の例外としての相殺
既判力の例外として、相殺があります。
既判力に関する特則が、民事訴訟法114条2項にあるのです。
「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する」
との規程です。
ある金銭請求に対して、相殺の抗弁を主張することがあります。自分も原告に対して債権を持っているので、それで相殺するという主張です。
相殺の抗弁は、判決理由中での記載となります。
判決理由中の記載では、原則として既判力がありませんが、例外的に相殺の抗弁が主張された場合の被告の反対債権については既判力を生じるのです。
既判力以外の信義則による拘束力
既判力は、訴訟物に限られますが、判決理由中の判断でも拘束力をもたせた方が良いというシーンもあります。
紛争解決の実効性を考えると、判決の理由中の判断についても、後訴への拘束力を認めた方が良いとする考えが提唱されるようになりました。
とはいえ、既判力としては条文上、認められないため、個別の事情によって、信義則により遮断するという裁判例が増えています。
学説上は、争点効と呼ばれる理論です。
最判昭和51年9月30日では、農地買収処分の無効を前提とする買戻契約に基づく所有権移転登記請求が棄却。
その後、買収処分の無効を理由とする所有権移転登記請求がされたケースです。
買戻契約か所有権かということで、訴訟物は違います。
しかし、裁判所は「本訴は、実質的に前訴のむし返しというべきものであり、前訴において本訴の請求をすることに支障がなかった」として、後訴を「信義則に照らして許されない」として却下しました。
ストレートに既判力の問題にならないとしても、実質的に同じ紛争であれば、信義則により制限されることがあるのです。
横浜にお住まいの方で、民事裁判に関する法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。